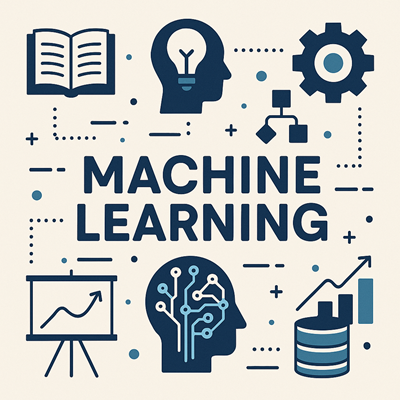ベクトルという言葉は、機械学習を学ぶうえで避けて通れない基本概念です。
少し抽象的に感じるかもしれませんが、ベクトルを理解すると、モデルが「どのように学習し、どのように判断しているのか」がぐっとクリアになります。
ここでは、ビジネスや実務にも応用できるレベルで、ベクトルの考え方を丁寧に解説します。
ベクトルとは「数の並び」ではなく「特徴の集合」
ベクトルとは、複数の数値を順番に並べたものです。
ただの数字の集まりではなく、「対象の特徴をまとめたひとまとまりの情報」と考えるのがポイントです。
たとえば、ある顧客を「年齢・年収・購買回数」で表すなら、それらを一列に並べたものがその顧客のベクトルになります。
同様に、画像ならピクセル値、テキストなら単語の出現頻度、音声なら音の周波数成分など、どんなデータも最終的にはベクトルに変換して扱います。
つまり、機械学習におけるベクトルは「データを数学的に表現するための共通言語」です。
ベクトル演算とは、モデルの“考える力”そのもの
ベクトルはただ保存するためのデータ形式ではなく、モデルが「考える」ための材料でもあります。
機械学習モデルは、ベクトル同士をさまざまな形で組み合わせ、比較し、変換することで予測や分類を行っています。
類似性を測る
2つのベクトルがどのくらい似ているかを調べることができます。
例えば、顧客Aと顧客Bの行動ベクトルを比べて「似ている購買パターン」を見つけるのもベクトル演算です。
マーケティングでは、これを応用して「似たユーザーへの広告配信」や「レコメンド」に活かします。
大きさを測る
ベクトルの「長さ(ノルム)」は、情報量や強度を表します。
モデルの重み(学習パラメータ)が大きすぎると過学習を起こすため、この大きさを抑える処理(正則化)にもベクトルの長さの概念が使われます。
モデルとベクトルの関係を直感的に理解する
線形回帰モデルの場合
入力データがベクトルとして与えられ、それぞれの要素に「重み」が掛け合わされ、最終的に予測値が算出されます。
つまり、モデルが「どの特徴を重視するか」を数値的に学習しているのです。
ニューラルネットワークの場合
入力されたベクトルが何層にもわたって変換され、より抽象的で意味のある特徴へと変化していきます。
たとえば、画像であれば最初の層は「線」や「角」、次の層は「目」や「口」といった要素を学び、最終的には「人の顔」として認識します。
このように、層ごとにベクトルが別の空間へと写し変えられていくのです。
意味を持つベクトル「埋め込み表現」
自然言語処理や画像認識では、ベクトルが単なる数の並びではなく、「意味」を内包します。
これを「埋め込みベクトル(エンベディング)」と呼びます。
たとえば、ある言葉をベクトル化すると、「似た意味の単語ほど近い位置」に配置されます。
この性質により、「男性的な言葉」と「女性的な言葉」の関係性など、意味的な構造を数値空間上で捉えることが可能になります。
ただし、すべての埋め込みが明確に意味関係を再現できるわけではなく、学習データや手法によって結果は変わります。
ベクトル空間で考えるという発想
ベクトルを扱ううえで大切なのは、「空間に点を置く」感覚です。
各ベクトルは、多次元空間の中の1つの点として存在します。
点が近ければ似ている、遠ければ異なる、この単純な距離の概念が、多くの機械学習アルゴリズムの土台になっています。
たとえば
- 類似ユーザーを探す「近傍法」
- データをグループ化する「クラスタリング」
- 情報を圧縮する「主成分分析(PCA)」
これらはすべて、ベクトルの位置関係をもとに動作しています。
PCAの場合は、データ全体の分布をうまく回転・圧縮しながら、情報をできるだけ保ったまま次元を減らす手法です。
完全に情報を保てるわけではありませんが、損失を最小限に抑えるよう工夫されています。
まとめ
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| ベクトルとは | 特徴をまとめた数値の集合 |
| 主な役割 | データの表現、類似度の測定、モデルの入力 |
| モデルとの関係 | 入力→変換→出力のすべてがベクトル演算で構成される |
| 実務での応用 | 顧客分析・広告最適化・レコメンド・テキスト解析など |
ベクトルは、機械学習を支える最も基礎的な概念でありながら、応用範囲は非常に広いものです。
もし次のステップとして理解を深めたいなら、「行列(複数ベクトルの集まり)」や「埋め込みベクトルの学習方法(Word2Vec・BERTなど)」を学ぶと、より実践的な理解に繋がります。
以上、機械学習のベクトルについてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。