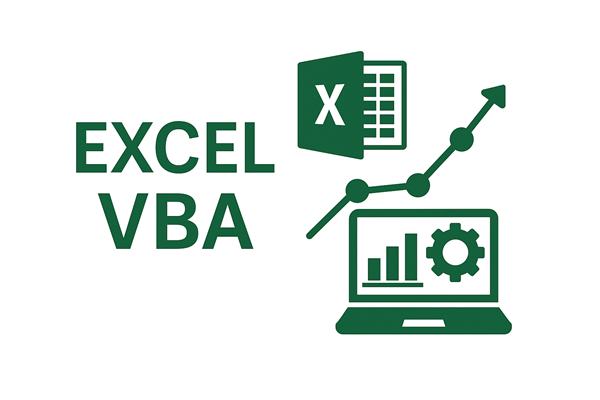Excel VBAで機械学習を行うということ
Excelはもともと「表計算ソフト」ですが、工夫次第でシンプルな機械学習(ML)を実現できます。
特にVBA(マクロ)を活用すれば、データの読み込みから学習、予測までを自動化することも可能です。
ただし、Excelだけでは大規模データや高度なAIモデルには向きません。
数千~数万件程度のデータを扱い、基礎的な分析・予測を効率化するツールとして使うのが現実的です。
Excelで機械学習を行う4つのアプローチ
ExcelでMLを実現するには、いくつかの方法があります。
それぞれの特徴を理解して選ぶことが重要です。
Excelの関数や分析ツールを活用
Excel標準の「データ分析」機能を使えば、重回帰分析などの基本的な予測モデルを構築できます。
「Solver(ソルバー)」を使えば、最適化問題としてパラメータ調整も可能です。
ただし、ロジスティック回帰などは自動機能がないため、自作関数またはVBAが必要です。
VBAでアルゴリズムを実装
VBAを使えば、学習・評価・予測を自動実行する仕組みを作れます。
代表的な例は次の3つです。
- 重回帰分析:数値の予測(例:売上予測)
- ロジスティック回帰:二値分類(例:購入する/しない)
- k-meansクラスタリング:データのグループ分け(例:顧客セグメント)
この方法なら、ボタン一つでモデルの更新が可能になります。
外部ライブラリを呼び出す
VBAからC言語や統計ライブラリを呼び出して高速化する方法もありますが、設定が複雑です。
導入のハードルが高いため、初心者にはあまり向きません。
ExcelとPythonを連携させる(現実的な最適解)
Excelを入力・出力のインターフェースとして活用し、裏側でPythonが学習を行う構成です。
xlwingsやPower Queryなどを使えば、Excel操作の延長線上で本格的なAI分析ができます。
現場でよく採用されている実用的な手法です。
機械学習の流れ(Excelでの実践イメージ)
Excelで機械学習を行う場合も、基本のプロセスは他のツールと同じです。
- データの準備と前処理
- 欠損値を平均や中央値で補う
- 数値の単位をそろえるために「標準化」する
- 文字データ(カテゴリ変数)は「ワンホット化」して数値に変換
- データの分割
- データを「学習用(例:80%)」と「テスト用(例:20%)」に分ける
- モデルの学習
- 勾配降下法などで最適なパラメータを求める
- 精度の評価
- 回帰:誤差(RMSE)や決定係数(R²)
- 分類:正解率、適合率、再現率、F1スコア
- 新しいデータで予測
- 学習したモデル(重み)を使って新しいデータを予測する
- 自動化
- VBAボタンを押すだけで一連の処理を実行できるようにする
シート構成のおすすめ
Excelで機械学習を運用する際は、シートを分けて管理するのがポイントです。
| シート名 | 役割 |
|---|---|
| Data | 元データ(特徴量と目的変数) |
| Config | 学習設定(学習率・反復回数など) |
| Model | 学習済みのパラメータ(重みや係数) |
| Report | 評価結果(RMSE・R²・混同行列など) |
| Predict | 新しいデータを入力して予測値を出す |
こうしておくと、どの工程で何が行われているかが明確になり、再利用もしやすくなります。
Excelで扱いやすいアルゴリズムと活用例
| アルゴリズム | 内容 | 典型的な用途 |
|---|---|---|
| 重回帰分析 | 数値の予測(線形モデル) | 売上やクリック率の予測 |
| ロジスティック回帰 | 二値分類(Yes/No) | 購入/非購入の分類 |
| k-meansクラスタリング | 類似データのグループ化 | 顧客セグメント分析 |
これらはExcelでも十分に実装可能で、業務改善に直結しやすい手法です。
マーケティングでの実例:クリック率予測
広告のクリック率(CTR)を予測したい場合を例にします。
- Dataシートに以下の項目を用意
- 広告の位置(上・中・下)
- デバイス(PC / スマホ)
- 時間帯(sin/cos変換で24時間を周期的に表現)
- 画像サイズや文字数
- 実際のクリック率(目的変数)
- VBAで自動学習を行い、重回帰モデルを作成。
- ReportシートにRMSEやR²を出力して精度を確認。
- 新しい広告案をPredictシートに入力し、CTRを自動予測。
これにより、どんな広告設定が高い効果を出しそうかを数値でシミュレーションできます。
実装・運用時の注意点
- 標準化は基本的に推奨
勾配降下法を使うときや正則化を導入するときは、数値スケールを揃えないと学習が不安定になります。 - データ規模の限界を意識する
数十万件以上のデータでは、Excelの計算速度がボトルネックになります。
数千~数万件程度を目安にしましょう。 - ロジスティック回帰はSolverでは自動化されない
Excel標準機能ではサポートされていないため、VBAまたはSolverで損失関数を定義して最適化する必要があります。 - k-meansは初期値に依存する
結果が安定しない場合、複数回試して最も良いクラスタを採用します。
クラスタ数kの決定には「エルボー法」などの目安があります。 - 分類のしきい値(0.5)は固定ではない
業務目的に応じて、再現率やF1スコアを最大化するしきい値を調整するのが望ましいです。 - 再現性の確保
データ分割や乱数の初期値を固定し、前処理や標準化の平均・分散を保存して再利用します。 - マクロの信頼設定
社内共有時は、セキュリティ設定で「マクロを有効化」する必要があります。
さらに高度な分析を目指すなら
VBAの範囲を超える場合、次のステップとしてPython連携が最も実用的です。
- Excelを入力・出力のUIとして使い、裏でPythonを動かす
→ これによりExcelの使いやすさを保ちつつ、
高精度なモデル(ランダムフォレスト、XGBoost、ニューラルネットなど)を利用できます。
この構成は、業務現場とAI技術をつなぐ最も現実的な橋渡しになります。
まとめ
Excel VBAでも、次のような範囲なら十分に機械学習を実践できます。
- 対象:数千~数万件のデータ、10~数十列程度の特徴量
- 手法:重回帰・ロジスティック回帰・k-meansクラスタリング
- 目的:数値予測・二値分類・セグメント分析
- 成功の鍵:データ前処理の一貫性・評価の可視化・再現性の確保
そして、より高精度や大規模な分析を目指すなら、Excelを入口にしてPythonとの連携へステップアップするのが最も効率的です。
以上、Excel VBAによる機械学習の方法についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。